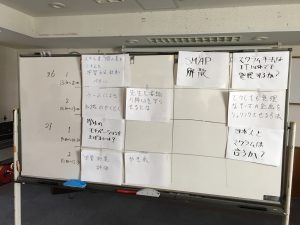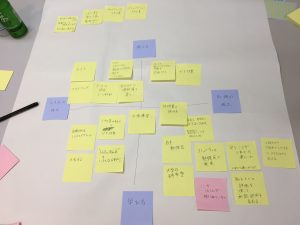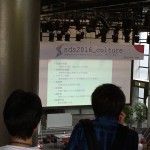ドナウ川を挟んでブダ+ペスト->ブダペスト
日曜日, 1月 29th, 2017去年の10月に行ってきたハンガリー出張の話。書くつもり無かったのだけど、お土産で買ってきた調味料化されたパプリカを今頃思い出して、丁度いいぐらいに料理するタイミングだったので作ってみたという話ついでに写真眺めてたら書きたくなりました。
<ブダペストってこんな所>
当時のツイートはこんな感じ。
- 2016/10/10: 乗り継ぎ乗り継ぎで片道移動だけで24時間。辛かった。
- 2016/10/11: 学会初日、近場散策で中央市場へ
- 2016/10/12: 学会2日目、会場でランチ取りつつ空いた時間でドナウ川向かいのブダへ。iPhone6sのバッテリー問題で落ちたのはここが1回目だな
- 2016/10/13: 学会最終日、終わった後に最後の散策
行ったのは10月上旬ですが、緯度的にほぼ北海道ぐらいの北側に位置してるだけあって既に冷えてます。日中は晴れてたら15度超えるぐらいはあるけど、曇ってたら10度切るぐらいには冷える。そこまで冷えるとは想像して無くて、最初の数日は沖縄での冬スタイルで過ごしてましたが、雨風強くなった中日で限界来て上着買っちゃいました。そのぐらい冷えてる割には「テラス席」を用意してるお店が多くて、実際利用客も大勢いる。風強い時は流石にほとんどいなかったけど、それでもゼロではなかったな。
散策してた際に知ったのだけど元々ブダペストという都市ではなく、ブダとペストが合体したらしい。ドナウ川挟んで西側のブダは確かに防衛考えたらそこにしろ建てるよなという場所で、見晴らしの良い場所。
散策して目についたのは、飲食関連だとパプリカとソーセージに、デザート。ホテルでやってたブダペスト観光PR情報によるとハンガリー人はデザートが好きらしく、実際学会会場になってたホテルでも「午前中の2セッションの合間にコーヒーブレイク(デザート)、昼食、午後2セッション合間にコーヒーブレイク」みたいにデザートがそこかしこで用意されてました。
伝統グッズだと、織物と陶器か。こっちは中央ストリートでもよく見かけましたが、それ以上に中央市場に集中してました。雰囲気的には「沖縄でいうところの公設市場を綺麗にした」感じ。1階は生鮮食品が多く、ソーセージ・パプリカ・農産物・パン・デザート・ハーブティー・ジャム等。2階は小物が多く、陶磁器・カロチャ刺繍・服飾・革製品・ボードゲーム(チェスっぽいのから良くわからないものまで)等など。見てるだけでも楽しい。あ、2階にはその場で食べるブードコーナーもあったか。
アジアンビューティー?的なものがブームなのか、市街地の至る所に「タイマッサージ」の看板が。個別の店舗だけじゃなく、インターコンチネンタルとかお高めのホテルの中にもあった。それ以外に目につくのは「両替屋と観光サポート」。両替屋はパット見普通なお店から「ここ、入ったら出てこれなくなりそうだな、、」としか思えないぐらいには怖い古びた&入り口が奥まったところにある建物まで、いたるところにある。観光サポートというかインフォメーションセンターの出張版というか、「パラソル立ててそこに一人二人サポートする人がいる」というのがあちらこちらにありました。公的なもので、海外観光客へのサポートが充実。無料・有料問わずあれこれコンシェルジュ的に対応してました。有料ともくんでるだけあって、割と短時間で丁寧なガイドツアーに参加できたり。観光立県とか観光立国とかいうならこういうの目指して欲しい。あ、ちなみに屋外のトイレは有料なこと多し。
お土産で買ってきたものはチョコ多数、パプリカ調味料3個、ソーセージ数本。肉類持ち込みデフォルト禁止だと知ったのは持ち帰った後で、関西空港でボッシュート。しくしく。
チョコは実家以外だと研究室や先生らに配ったぐらいでおなくなりに。残ってたパプリカ調味料を今日使ってみました。使い方よくわからないのだけど、パプリカ煮込みぐらいでググると基本的には単純な煮込み調味料として使って問題なさげ。手元にあるのは3つあるのだけど、一度にすべて開けるのは勿体無い精神が働いたので、今回はチューブのみで挑戦することに。煮込む前に具材を軽く油通しして、煮込む準備。問題は分量ですが、写真のチューブタイプだと「味噌」の分量ぐらいで良さげ。塩で整えて終了。本場で食べたのとは見た目も味も大分違いますが、食べ終えた後の風味は似てるな。多分、単純に煮込むだけではなく事前に漬け込むとか、複数種類使い分けて合わせ味噌的に「うちに代々伝わるパプリカ煮込みをどうぞ!」とかやってるんじゃないかと想像。