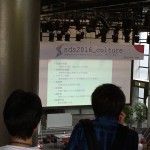情報工学科では学生による授業評価結果がweb公開されてます。プログラミング1を初担当したこともあって、純粋な授業そのものへの評価というだけでなく、前年度と較べて大きく違う点があるのかが気になります。英語教科書指定したり、ペアプロ導入したりしてるし。
上記の比較対象が2015年度ではなく2年前の2014年度になってるのは、システムトラブルか何かで参照できなかったため。後で報告しておこう。
Q2のシラバスの効果に関する設問では、「役に立った」が2014年度は29名(約67%)に対し、2016年度は46名(約80%)と大きく向上。実際シラバスや授業ページはかなり細かく準備しており、学生にも受けが良かったようで一安心。一方で、「どこに何があるか」を探すのが辛かったりはするかも。ちょっと整理が必要だよなと思いつつ、整理するのは学生自身のタスクだろうという気持ちも。どうしようかな。
Q3のテキストの役立ち度合いに関する設問では、「とても効果的だった+まあまあ効果的だった」の2つを合わせた数値で比較すると、2014年度は21名(約48%)に対し、2016年度は29名(約50%)。ほぼ一緒ですね。英語でも問題なし、と。一方で、最終課題の取組状況を考慮すると、この29名は恐らく好成績を残した上位陣で英語でも読んでた層。残りの学生は読まずに理解不足(未だに関数やインデントがよく分かってない学生もいる)な層だと想像。教科書読めば一発で分かることが多いですが、読まないのだよな。
Q4の補助教材の役立ち度合いに関する設問は、Q3と類似の傾向。ちなみに、シラバスや教科書、補助教材が「なかった」と回答する学生が例年いますが、正直言ってどうしようもないですね。
Q5の教員説明の分かりやすさに関する設問は、「とても分かりやすかった+まあまあ分かりやすかった」の2つを合わせた数値で比較すると、2014年度は10名(約30%)に対し、2016年度は45名(約78%)と大きく向上。これは説明が分かりやすかったというよりは、ペアプロ演習を増やした点と、C言語よりはPythonの方が取っ付きやすいよね、という2点の影響が大きい気がします。
Q6の板書やスライドの見やすさに関する設問は、「見やすかった」が大きく増えてるか。拡大するようにしてるし。
Q7の教員の声の聞きやすさに関する設問では、誤差ぐらいの改善。
Q8,9の演習中の教員指導のわかりやすさに関する設問ではほぼ同じ。
Q10の講義難易度に関する設問では、「難しすぎた+難しかった」の2つを合わせた数値で比較すると、2014年度は37名(約86%)に対し、2016年度も46名(約80%)とおぼ同じ。最終課題は難しかったしね。
Q11の課題難易度に関する設問は、Q10とほぼ同じ。切り分けにくいよね。
Q12の週平均自習時間に関する設問では、「3時間以上+5時間以上」の2つを合わせた数値で比較すると、2014年度は28名(約70%)に対し、2016年度は18名(約31%)に激減。最終レポートの出来具合からみても「ちゃんとやってるな」と感じるのはこのぐらいの人数なので割と実感にも合ってます。
その他、講義がためになったか(Q19)、講義の理解度(Q20)、あたりはほぼ同じ。
自由記述回答の設問については、
日本語教科書欲しかったとか書いてる人いますが来年も英語のままにします。
ペアプロについて、「ペアプログラミングはコミュニケーションが極度に苦手な人にとっては,休学や中退に至るほどの危険性を伴うものだと,私個人の経験から思っている。そういった人を早期に発見し,何かしらのフォローが出来る体制を整えるべきだろう。」や「 ペアの人が予習や復習をしていないと、演習が止まるので、どうしたらいいのか困った。」と指摘してる点については把握しつつも、良い対応が思いついていません。試行的に、後期授業(プログラミング2)で冒頭数週間のペアプロでは「学生自身がパートナーを選ぶ」形にしようかと思ってます。「できる人に習う」よりも「話しやすい人とやる」方が良いかもしれない、という可能性もあるので。
話し方について「少しだけゆっくり話してほしい わからなくなった瞬間に置いていかれて、どこやってるのか全くわからなくなる」という指摘は、そうかも。意識してゆっくり話さないと、かなり早口になっちゃうのだよな。
その他、「助け合わないと単位を落とすと思う」や「一番力がついたのは課題の時だと思う。」あたりは狙い通りになったようで、良かった。