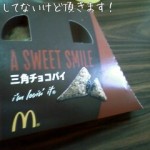木曜日は比較的固定タスクがないので融通聞かせやすい一日なんですが、逆にその分あれこれ入れてしまって他がやれなくなるということも。ということで今日は結果的には丸一日デザインスクール関連な一日でした。
午前中は、遠藤先生と一緒に 観光産業科学部の下地先生との打ち合わせ。リンク先はググったら見つかったやつだけど、今度読んでみよう。今回のデザインスクール(ワークショップ)の目的とテーマ・進め方について説明してみた結果、実はテーマA(街並みデザイン)の方は今丁度研究生が取り組んでるテーマということもあってその学生には参加してもらえそう。テーマB(おもてなしデザイン)は観光業では共通するということで誰かは釣れそうらしい。ということで、観光科学科の学生も数名は参加確定っぽい。基調講演の方も「そもそも何故今の沖縄がこういう状態になっているのか」ということについて歴史的背景絡めた話をあちこちでやっているということで、快諾頂けました。ありがとうございます!


下地先生の学生さんらによる研究研修してきた発表会が昼過ぎからあるということで、そちらに参戦。「かりゆしホテルズ観光人材育成基金」ハワイ大学研究プログラム報告会というもので、去年から始まってる取り組みらしい。大きな目標としては「テーマを決めてハワイ大学の研究プログラム(講義等の受講)をしつつ、フィールドワーク。テーマに関する沖縄との共通点/違いを整理して報告」というものようです。一ヶ月ぐらい(?)の比較的期間の長いプログラムであることと、次で述べるように琉大(教員)も関わっているプログラムになっている点が大きな違いか。
国内での多数を占めるであろうインターンシップだと、(a) たかだか1~2週間程度会社見学+αして終わるか、(b) 新人社員の教育を兼ねて面倒見させながら作業してもらう、(c) その企業で採用している人材育成プログラム的なものに乗っかるか、ぐらいのいずれかであることが多そう。共通点は「基本的に丸投げ」。その方がやりやすい側面もあるだろうし。一方、観光科学科でのプログラムにおける研究プログラムの特徴は、インターンシップ先に丸投げじゃなくてあくまでも大学(教員)も関わった研究なりの共同作業の一環としてプログラム化しているところ。最初から具体的な目的や背景は勉強してる状態から始まるのでモチベーションは当然あるし、アンテナある状態で実地研修するのでいろんな視点を体験しやすく、現場ならではの問題の気づきやより具体性/現実味のある提案に繋がっている。ように感じました。
ちなみに研究プログラムに行ってきたのは4研究室(4グループ)らしく、ざっくりとしたテーマは以下の通り。(聞き違いとか誤釈多々あるかも)
- スポーツツーリズム@辻グループ
沖縄と言えば海だが、閑散期に観光客をどう呼び込むか。例えば野球キャンプや那覇マラソンは既に認知度が高い。トレッキングやトレイルランニングは世界的に広まりつつあるが、沖縄ではまだまだ。問題点をどう洗い出し、それらに対してどういう提案ができそうか。
- 景観政策@下地グループ
沖縄には景観法(景観規制)が準備され、ガイドラインを元に市町村毎に取り組みが始められつつある。しかし一般住民レベルでは認知度が低い(20%以下)だけではなく、景観について良し悪しをあげることができない。これがハワイだと80%以上の住民が認知していて、その良い点も悪い点も指摘することができる。観光客からすると「沖縄らしい街並み」を求めているし、地元の人は「暮らしやすい街並み」を求めているだろう。それらを両立させるためにはどういう施策が考えられそうか。
- 観光の資格@井川グループ
沖縄でもハワイでも人事担当からすると資格そのものはそれほど重要視しておらず、実践できるかどうかが問われる。特にハワイでは質の高いパーソナルテストを実施している点が異なる。また、沖縄だと抽象的な資格や目的(語学とか)だけを持ってる人が多いのに対し、ハワイでは「ホテルの○○」というような具体的な業務を目的に取り組む人が圧倒的多数。これらを踏まえて、大学における観光業人材教育において、理論と実践を組み合わせた形は考えられないか。
- 格付け制度@上地グループ
ホテルやレストラン等におけるハード・ソフト面における格付け制度は、それを望んでいるカスタマーがいるからこそ。一方でそれだけでは語れない側面があるのでは。例えば「ハワイらしさ」や「沖縄らしさ」を導入することはできないだろうか。
仮に情報工学科で似たようなことをやろうとするとどうなんだろう。インターンシップじゃなくて最初から共同研究で良いじゃんみたいな話になるのかな。知的財産的にいろいろ面倒な状況がありそうではあるし。