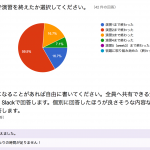(Java本)全部を取り扱う都合の良い本は無さそう
火曜日, 5月 17th, 20161年次後期に使うJava本探しにジュンク堂であれこれ探してみました。那覇店にも洋書の専門書があったような気がしたけど、今はもうなさ気か。ということで今回は和書のみのチェック。隣の棚にAndroid本もあって「そっちでJava&オブジェクト指向導入するのもありか?」と数冊眺めてみましたが、やっぱりなしだな。達成目標に対して回り道過ぎるので。
オライリー棚とか一部にJava関連がある棚含めて4つぐらい棚をチェックしたところ、大雑把に分けると次のようなタイプに別れるのかな。跨ってるのもあるとして。
- (1)Java言語解説書(言語仕様解説書)
- (2)特定機能についての解説本
- (3)取り敢えずコード書けることを目指したチュートリアル本
- (4)オブジェクト指向開発解説等、設計中心本
- (5)デザパタ本
- (6)リファレンスやクックブック的な本
- (7)周辺知識本
「1冊だけ」という縛りを入れると授業で扱いたいこと(オブジェクト指向プログラミング解説+Java8+コード多め)を一通り触れてるものは無さそう。普通はそうだよね。今やってるPython本もそれ踏まえて足りないところは補う形で使ってるし。何を補うかという点からは、年々updateされる言語最新事情についてはひとまず置いておく(補足対応する)というのがベターかしら。
「Java言語仕様ついては基本を抑えるぐらい、オブジェクト指向プログラミング解説とコード例多め」を基準とすると、眺めた書籍の中での候補はこんな感じ。良さそうな順。
- スッキリわかるJava入門 第2版 (2014)
- 新わかりやすいJava入門編 (2015)
- 新・これならわかる Java (2008)
- 理工系のJavaプログラミングテキスト (2004)
帯に「完全独習テキスト」と書いてるだけあって予習復習に向いてそうなのは「新わかりやすいJava入門編」。一方で楽しんでやれそうなのは「スッキリわかるJava入門 第2版」かな。特に「スッキリ」の方はスタックトレースの読み方、エラーメッセージ一覧、構文リファレンスとか痒いところも整理してくれてるのは良さそう。ただし全体的に「対話やり取り」での説明が多く、ぱっと見でどこにに何書いてるかが分かりにくそうなところが難点に感じます。最初から一通り通すだけならそれで良いんだけど、復習するのが辛そう。(復習考えると前者のほうが良さそう)
あと、Java言語プログラミングレッスン第3版が、まだノーチェックで気になる。
少し違うアプローチとして、UMLを交えて設計中心で話が進む「UML&Javaオブジェクト指向開発」も、選択子としては捨てがたい。別の講義で、モデリングと設計があるからそっちに任せるので良いとは思うんだけど。
名前だけ聞いたことがあった「EFFECTIVE JAVA 第2版」はどうかと思ったんですが、これは一度Javaを勉強した後で参考にするノウハウ集なのね。