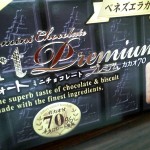まだ湿度が高めだけどそろそろ梅雨明け?という天候具合。起きた時点では外出するか悩んでたんですが、ここ最近ずっと籠ってたのとジュンク堂であれこれチェックしたいのとがあって出かけることに。結果的にはにわか雨があったっぽいのだけど運良く濡れず、日差し強い間は折りたたみ傘(雨傘)を日傘代わりに使って凌ぎつつでどうにか遠征終了。木かげカフェが閉店してたのはショック。ステーキに走ってから謎な方向に進んでるなとは思ってたけども。。


ジュンク堂方面行く頻度がめっきり減ってることもあって「行く度に久しぶり」という状態。久しぶりならゴカルナへ行ってしまって新規開拓してないな。いや、ゴカルナさんが「今月のカレー」とか毎回新しいカレー出してる(少なくとも私は同じのを見たことが無い)から毎回違う物を食べてるのだけど。食後のラッシー・マーマレードで一休みしつつ積本になってた小説ちらほら。まだイントロだけど面白そう。
汗が引いてからジュンク堂へ。平和通り通って行くので影が多いのだけど食事したばかりの真昼に歩くとあつあつ。なるべく汗かかないように/汗拭きながら移動。ジュンク堂は真冬かと思えるぐらい空調効かせてるから汗かき過ぎた状態で入るときついのだよ。。今日は調べたい物があったのであれこれチェック。具体的には平良くんの「小説を読んだ時に生じる感情をどうモデル化するか」について、そもそもどこまで心理学/認知心理学/認知科学周りで論じられてるかをチェックしたいなと。附属図書館があるので「数週間図書館籠って書籍/雑誌(論文誌)を漁って来い」でも良かったんだろうとは思うのだけど、気持ち的にジュンク堂へ。気がつけば2時間強眺めてたらしい。

ざっと眺めた感じでは「コレクション認知科学シリーズ」は一通りゲットしても良さげかなぁ。取りあえず今回は第3巻「視点」と第10巻「心の計算理論」を購入。
第3巻「視点」では、視覚的な視点も含みますが後半からは文学作品をどのような視点で関わり、作品やそれを構成する要素をどう認識しようとするかという事例が紹介されているらしい。佐伯先生(1978)の「小びとモデル」では、「視点を設定するとは自己の分身としての”小びと”を生み出し、対象に派遣してみることである。派遣された”小びと”がそこで様々に動いてみせることをとおして、人間は世界を理解していく(p.130)」らしい。他にも「中の人(例えば小説内の主人公)の情動をどう把握するか」についても「文学での心情理解のみならず、他者理解のいろいろな領域で使われている先方方略(p.139)」とか。こういうモデルを考えてる人いるだろうなと思いつつ原典(?)ぽいのが見つかったのは良かった。
第10巻「心の計算理論」では、記号処理(日本語や英語等で書かれた文章は記号で書かれた文書で、これを人間はどう処理しているのかという視点から取り組んでる分野)な話で、例えば記号そのものだけではなく「ゴールとプラン」という感が方を導入することで見えてくる背景/文脈があるが、それだけでは感情推論がうまくいかないケースがある。例えば「花子は太郎にふられてしまいました」「花子は家に帰ってくると、犬のワン子をけとばしました」について、認知的推論においては1文目で「花子は自分のゴールのうち一つの達成が太郎によって妨げられたと考えている」と推論することができるが、これだけでは2文目の解釈には役に立たない。そうではなく「花子は(覚醒水準の)負の状態にある」という推論をすることで、2文目の解釈が可能になる、という話(p.134)。
「文章理解の心理学―認知、発達、教育の広がりの中で」は、文字通り「文章をどう理解するのか」について様々な視点から整理された本。例えば「語の意味」「物語のおもしろさと情動反応」「文章理解のコンピュータ・シミュレーション」「文学作品における理解」「マンガの表現構造に着目した記号分析と計量の試み」等々。ちなみに「文学的なテキストの味わい、鑑賞などについての実証的な研究はあまりなされていない(p.200)」らしい。少しは参考文献示されてるけど。でも、されてないならされてないで面白いよね。
「心理学基礎演習 Vol.2 質問紙調査の手順」は、紙でアンケート調査する際の一般的な方法論について整理された本。具体的に「こういう質問文にしよう」というレベルの話ではないけども、最終ゴールをどう思い描くべきか、それを想定した上でどうアンケートに落とし込むか、それをどう分析するか、、等がまとまっているので参考にはなるのかも。

それなりに満足したので、琉球珈琲館へ移動して休憩しながら読書。シークワーサースフレが無かったのが残念。