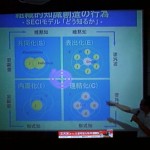就職センター中の人話、PostgreSQLリストア済んだその後
金曜日, 7月 4th, 2014今日で実験1が入り込んだ忙しい週が終了。実験4コマ、授業1コマ、ゼミ3コマな週でした。別タスクとしては、デザインスクールでのテーマとして設定できそうかの下調べとして就職センターに話を聞けたか。
実験1/ネットワーク演習1は、レポート課題ではなく実技テストのみで、一応今週出席した人らは大丈夫の模様。欠席者にはメール通知済みですが、今の所一人しか反応ないらしい。もう後半だし、そういうものだろうなとも思うけど、時間も授業料も勿体無いな。
PostgreSQLリストア問題は、一通り解決。結果的には8カ所にエンコード上の問題がありました。思ったより少なくて良かった。ということで後はリストアしたやつに収集スクリプトで追加していくだけ。だと思ってたんですが、これが微妙にうまくいかない。rootで動くことも確認済みなんだけど、cron実行すると動かない。せめてエラーログ吐いて欲しいんだけど。って、そういうスクリプト噛ませば良いな気もするな。でもちょっとこれ以上追求したくない気分なので、週明けまで放置プレイで。
就職センターではわざわざセンター長を初めとして3人もが時間割いて準備してくれてました。何だか申し訳ない。就職センターとしては、直接的な就職活動支援だけではなくインターンシップ/アドバイザ(キャリアカウンセラー)、その他の企画イベント(例えば企業見学)等の提供を通して「卒業生らの進路決定率(not就職率)」改善に繋げることを目標としているらしい。進路決定率を意識しているのは、「就職率」はちょっとしたマジックナンバーで母集団が卒業人数とイコールではないため。具体的には、昨年度の進路状況として公開している就職率88.3%は「就職を希望していて就職できなかった割合」であって、その隣りにある「その他」の255人は「卒業してるけど就職を希望していない人も含む(公務員/教員志望等も含む)人数」で、進路自体を決定できていない人数がかなりいるという話。
聞きたかった話は「沖縄ならでは」の話について。伝聞では「沖縄の人は辞めやすい」とかありますが、そこら辺の数値/何かしらの体験談や、就職相談等を通した県民特性なりがあれば是非とも、という気持ちで突っついてました。あいにくというか就職センターとして卒業生の追跡調査は困難なのと、企業への質問アンケート等も回答率が悪いために統計的な情報や分析はできていないらしい。ただ、就職活動支援(旅費2.5万支給)に伴う報告書を眺めたり、報告会を開催している限りでは「県外学生のアクティブさに驚いた」ケースが多いらしく、一度参加することで意識に変化が見られる学生が少なくないとのこと。その大きな要因は、沖縄が海に囲まれた小さな島(で競争相手が少ない)ことや、親御さんが必要以上に過保護にしてたり、求人自体が少ないにも関わらず最初から外を知らないので県内指向といった、県民性に根ざした問題かもしれない。という話でした。とにかく「一歩踏み出して外に目を向けよう!(あれこれ手を打ってみるがそもそも学生が来ないケースが多い)」とのこと。うん、そうだよね。B2にブログ課題やらせてるのもその一貫だし。「辞めやすい」については、恐らく事前の企業研究不足によるミスマッチではとのこと。どう調査したら良いか、そもそも調査自体していないことも少なくないとか。
個人ゼミは高橋くんの番で、やりたいといってる情報推薦とはどのようなものか、について少しずつ周辺情報を書き出し、説明し合いながら互いの認識を共有。同じ言葉でも違うことを意味していることが多々あるので、いろいろ表現し直してみるというのが重要。この過程を通してぼんやりしてたイメージを少しずつ具体化していくことに。ただ、最終ゴール自体が決まってる訳ではないので途中からは「具体例を例示」したり、「それらを抽象化することで課題例を提示」したり。テーマに落とし込む所まではやってないですが、参考になるかもしれない文献渡しつつ、咀嚼兼ねて自分なりに整理&再検討してもらうべく宿題として持ち帰り。
お疲れモードなので月曜日はお休み。ということで3連休〜。