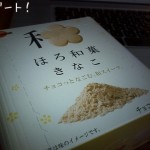今週はe13の個人面談ウィークです。1対1で対面式で話をするという機会の提供でもあるし、早めにテコ入れした方が良さそうな学生の発掘でもあるし、どんどん先に進んで欲しい学生へのアドバイスをする機会でもあるつもりですが、一人あたり5分+αぐらいしか取れてないので何かしらの切っ掛け提供以上のことにはなってないかも。それでも「何となく情報工学科入学した」とか「こういうことに興味があるけど具体的には行動してない」から一歩前進する切っ掛けになれば。
初日から一部来てない&連絡も無い学生が既に居ますが、ま、そういうもの。そういう学生は後日呼び出し対応するしかない。
以下は複雑研全体ゼミを終えての補足記事です。
来週で1巡目が終了になります。
再来週からはゼミの目的を変更し、トピック毎に掘り下げて基礎〜応用について皆で勉強するということを主題にします。各学会誌の特集記事や、専門書等から複数人でグループを組み、分担して説明できるように準備してください。リソース(特集記事や専門書等)についてはいきなり確定するのではなく、事前に候補として提案してください。問題無ければそのままそれを担当してもらいます。
以下、今日の全体ゼミ討論中に出てきたキーワード
・松田昇悟: [1] テキストの意味や意図
・平良浩嗣: [2] マンガ推薦
での関連話を補足します。
(NAL研MLでピックアップ済みが多いです)
[1] 文間関係認識のための構造的アライメント, 言語処理学会 第16回年次大会 (NLP2010), E3-7
[2] マンガの概要に基づく作品推薦システム, 第11回情報科学技術フォーラム (FIT2012), N-013
>テキストの意味や意図
2つの文間関係を判別するというタスクにおいてアライメントを用いた一例として [1] を紹介していたかと思いますが、このような文間関係を使って談話を理解しようとする試みの一つが「修辞構造 (rhetorical structure)」や「修辞構造理論 (RST)」と呼ばれています。
NLP2013からの例では、[3] は単一文書要約に、[4] は論理構成の整然さ評価に、[5]は応答文生成に、というように応用例の幅は広いです。どういう応用を見据えるかによって、その基礎を積み上げていくかも変わっていきますので、何かしら具体的なタスクを想定しておくと良さそうですね。
[3] 談話構造に基づく単一文書要約, 言語処理学会 第19回年次大会 (NLP2013), A5-1
[4] 文章構造解析に基づく小論文の論理構成における整然さの自動評価, 言語処理学会 第19回年次大会 (NLP2013), B3-1
[5] 対をなす二文書間における文対応推定および応答文生成への応用, 言語処理学会 第19回年次大会 (NLP2013), B3-3
>マンガ推薦
技術的には情報推薦に興味があって、その一例としてマンガにも興味があるということで [2] を紹介していたかと思いますが、自身でも疑問に感じていたように「そもそもストーリーを表現できているのか」「ストーリー特徴だけで推薦できるのか」という点では不十分な点もあるようですね。
「ストーリー」をどう捉えるかという点では、物語生成の分野で「プロップ理論」に基づいた事例がいくつか出ているようです[6,7]。
ストーリー以外の要素として、[8] では「スピード線」の違いが知覚に及ぼす影響について調査したようです。[9]は概要しか見れませんが、マンガ教材における影響について討論しているようです。同じグループらによる別の発表が [10] で公開されてますね。
[6] プロップに基づくストーリー生成機構と状態管理機構との結合, 言語処理学会 第19回年次大会 (NLP2013), P1-14
[7] 『物語の森』ー物語生成システムの統合的応用の一試行ー, 2012年度日本認知科学会 第29回大会, P1-29
[8] スピード線描写の違いが速さ知覚に及ぼす影響, 2012年度日本認知科学会 第29回大会, P3-14
[9] マンガ教材学習における登場人物の視覚的特徴が印象に与える影響, 第6回エンターテイメントと認知科学シンポジウム 資料
[10] マンガ描画技法が学習者に与える印象の分析ーマンガ教材の品質改善に向けてー, JSiSE 2012, http://www.jsise.org/taikai/2012/program/contents/pdf/E4-1.pdf