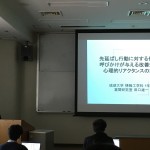一昨日締め切られた修論からはや二日目(平日という意味では1日目)、あまり時間的にも余裕ないしということで一人目の予備審査が終了。
予備審査はオープンにしてるものではない(原則として聴講参加できない)ので置いとくとして。今日は博士後期課程2名の公聴会もありました。赤嶺研の上原くんと、宮里研の早乙女さん。上原くんは「デマンドバスの配送経路計画を最適化しやすくするために、階層型エリア分割を導入した」というような話。マクロシミュレーションとミクロシミュレーションの双方から良し悪し分析してて面白い。でも運転手側のスケジュールがブラック気味らしいのは問題ありですねw。早乙女さんは「海洋資源調査を効率良く行うための海中通信と洋上通信という両方の無線通信の改善」という話。海中の方は和田研もやってる話にかなり近い。洋上は宮里研自身や玉城先生もやってる突発的な降雨をどうにか高精度で予測したいというもの。海中は基礎技術の確立という側面が近かったか。どちらもおもしろ話でした。
公聴会は最終審査でもありますが、「卒業研究最終発表」に相当よりもオープンなもので、基本的には誰でも参加できます。だから「公聴会」と名付けられてます。そういう位置づけのイベントですが、正式告知は学部事務による掲示ぐらいで大学サイトで検索しても数年前のが上位に来るというお寒い状況。2016年にしてこんなことで良いの?と思うのだけど。
教員側も参加者はほぼ主査副査のみに近く、他はその研究室学生がメインという感じ。一部身内の方もいらっしゃってたか。研究推進と掲げつつコミット具合が足りてないんじゃないかなぁ。公聴会が全てというわけでもないし、コミットの仕方にはいろいろあっていいと思うけど最後は華々しくやろうよとも思うわけで。ただ「博士進学者が少ない」と嘆くだけじゃダメだよね。
P.S.
私の公聴会の時はちょっと事情(注記)があって、ただの公聴会というよりはがっつり審査される(主査副査から質問攻め)という状況になってました。面白かった(やってること喋れれてそれについて本気で突っ込んでくれるってのは嬉しいよね)けど、そういうのは本来は予備審査で終わってるもので、公聴会でそうなるのは珍しい形だったらしい。
(注記)
私の場合は博士3年目の時に丸々1年間留学渡米してて、予備審査の時に一時帰国することができませんでした。予定ではするつもりだったのだけど、留学中にも「留学先で学んでることとは別に研究発表での出張もしてた(アメリカ国内で1回、国外(イタリア)で1回)」のが目に留められてしまって、「まだやることあるのに帰国するの!?」とか言われちゃいました。最初からそういう相談して許可もらってたんですけどね。