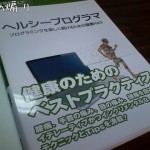2015年度プロジェクトデザインI, II 最終発表が終了
金曜日, 8月 14th, 2015あれこれ多くのことを名嘉さん&翁長さんに丸投げしての発表会が無事に終了しました。受講生の皆さんもですが、サポートしてくれた院生PMの皆さんもおつかれさまでした。
1年次のPD1ではテーマ自由(新規性・有効性・社会性のあるデザイン)をグループで企画提案せよという課題が。2年次のPD2では情報工学科のCMをグループで企画提案せよという課題が各々与えられていて、それをプロジェクトと看做した上で院生がマネージャとしてサポートに入ってもらっています。
PMのお陰もあってか、年々「ただのウケ狙い」というのが減ってるな。ネタを昇華してる。まだ突っ込みたいところ(サーベイ不足、シミュレーション不足、etc.)はあるが、それ含めて演習だし。という意味でもう少し細かくフィードバックしたいよなとは思うが難しいんだよな。また、前日あたりに発表練習するというグループも増えてて、PMに添削指導して貰えたところもあったようです。添削してもらえたことは次に活かそう(同じ失敗をしないように要因分析するなり対策検討するなり反芻・咀嚼しよう)。
PD1について例年気になってる点としては、新しいモノを考える・生み出すのは大切なことなんだけど、その過程を通して「調査研究」の大切さに気づかせる側面がまだ足りてないという印象があります。他と比較できないと「新規性/社会性/有効性」とかを主張できないはず(=企画に説得力を持たせ難いはず)なんだけどね。仕方ないのかもしれないけど、そういうことを1,2年次の頃にやってないから3,4年次になって苦労してるようにも見えるし。何か上手いやり方ないかしら。
一方で特に指示無いにも関わらず自主的にやってる良い面もあって、想像でターゲットの考えをでっち上げるのではなく100人にアンケートしてみたとか、学科外・学部外の人にどう思われてるか聞いてみたとか足で稼いでるグループがあったり。どこかが実施した調査結果を引用してるグループもあったか。そういう調査結果は便利ではあるけど、誰がどういう方法で実施したのか、回答者に偏りが無かったのか、設問文や選択肢等に恣意性が無かったか、回答当時と今とで同じなのか等々、様々な要因で「本来とは違う結果に引きずられる」こともあるので、単に結果を鵜呑みにするのは危険なんだよね。その意味で「自分たちの足で稼ぐ(アンケート実施する)」というのは、どういう偏りがあったのかとかも含めて話を進められる分、良い面もあります。
PD2について気になった点としては、「CM完成にこぎ着けなくても良い、その代わりちゃんと企画した内容を説明してくれ」ということは伝えているのだけど、「時間の都合上動画作成が簡単な案を選択した(ように見える)」ケースが去年も今年もあったこと。本来の趣旨はCMを作ることが目的ではなくて、CM作製のための企画立案を通してシラバスの達成目標をクリアできる力を磨くこと。なんだけど、多分去年もそうでしたが「他のグループちゃんと動画作ってるっぽいよ?」という状況になってたら、「うちも作らないとマズいのでは?」という気持ちになるのだろうなというのは理解できます。この辺りはどうしたものかなぁ。