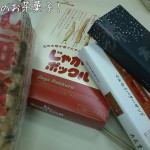デザインスクールのテーマにはやはり沖縄色を含めましょう、という流れに
金曜日, 5月 23rd, 2014今日はデザインスクールの打ち合わせで、京大側とのオンラインミーティング1回目。前回一度実施したということもあって、昨年同様にやるのか/やれるのか、違いがあるとしたら何なのかという点についての自由討論という形。それは良いのだけど、遠藤先生/山田先生/私(と、こっそり名嘉さん)というメンツでど真ん中が私というのは違うでしょう〜〜〜。厳密なリーダーを決めず、その場その場で合意方式で進めていくアプローチもあるのだけど、方向性ではなくて進め方の点で中途半端だと進みにくくてちょっと。
今回の打ち合わせで決めたっぽい大きな方針としては、(1) 沖縄で開催するから沖縄色を含む or 京大側サマースクールとの違いがあった方が良い、(2) 社会問題に限定しないがもう少しクリティカルな課題設定が良いのでは、(3) テーマ募集型にするならどこまで広げられそうか(会場との兼ね合い含む)、ぐらいかしら。個人的には絞り込まないと行けないほど集まったらそれはそれで成功だという話なので気にせず、とにかく大風呂敷広げよう〜とか思ってたんですが、微妙にそうもいかず。結果としては優先順位付けて声かけすることに。この記事読んでる貴方に声かけられるかもしれません(ニッコリ
沖縄を絡めたテーマ設定、どうしようかしら。(去年考えたのをもう一度やり返すのはちょっと少しとてもかなり気が思い)
P.S.
明日の通院日で実家に戻っているんですが、モカの体調が更に悪く。いや、今現時点では改善傾向にあるのだけど。お腹に水溜ってたり、心臓悪くなってるのとで薬をあれこれ出されてて、それをうまく食べさせるための工夫でてんてこ舞いらしい。というのを目の当たりにしました。5月頭は起き上がれないぐらいだったのが、今は立ててしっぽも動かせて、食べる量も少し実回復中。でもオヤツセット(気分次第で食べたい物が変わる)から一つずつ出しては食べたがるかを確認する作業は笑ってしまった。嫌な物は全力で否定する元気があるし。