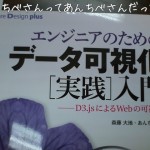情報処理学会前日は初参加組みへのアドバイス
月曜日, 3月 10th, 2014情報処理学会第76回全国大会が明日から始まるというこで、今日から金曜日まで東京にいます。天候的には木曜日から雨になりそうか。
うちの学生が発表するセッションは優先参加するので、調整しやすいのはそれ以外の時間帯。といいつつ同じ時間帯でブッキングしてる発表もあるので全学生分を見れるかは怪しい。面白そうなのが見つからなければ展示眺めに行っても良いし(学会会場で割引販売とかは良くある風景。電子版の割引コードくれとか思わなくもないな)。とはいえ大量の発表(30セッション並列+1〜3イベント企画同時開催)があるので、正直見たくても見れないというのが多い学会でもある。お祭りですな。
取りあえずイベント企画を斜め読みした限りでは以下のような日程になりそう。途中で気が変わって一般セッションに行くかもしれませんが。
[1日目の予定]
- 午前: 1P会場: 情報抽出 (堀川くん発表)
- 午後1: 招待講演1: IEEE Computer Society 2022 Report
- 午後2: 招待講演2: SW enabled IT industry development strategy in Korea
- 午後3: イベント企画: 人間を超えたコンピュータ将棋はどこへ向かうか
[2日目の予定]
- 午前: イベント企画: 「学会へ行こう!若者の夢を実現できる場所」-学会が若者にできること、若者が学会にできること-
- 午後1: イベント企画: 企業で活用される自然言語処理技術
- 午後2: 4P会場: 評判・感情・意味解析 (平良くん発表)
[3日目の予定]
- 午前: イベント企画: 知のコンピューティング― 知の創造促進と科学的発見・社会適用加速―(PD2的には大学における一般情報教育の現状と展開も気になる)
- 午後1: 基調講演: ビッグデータの今
- 午後2-1: 6P会場: 言い換え・関係抽出 (松田くん発表)
- 午後2-2: 6C会場: 自然言語処理(基礎) (慶留間くん, 玉城くん発表)
晩ご飯は会場(東京電機大学 東京千住キャンパス)への移動方法確認を兼ねて北千住に集合。オムライスの卵と私に突撃してみたのですが、旨いけど期待してたほどではないか。これならダブルデッカーの方が。あ、カボチャプリンは大変宜しかったです。
晩ご飯食べながら初めて学会参加する学生へコメントあれこれ。先輩からは「外部からのコメントを貰える機会なのでそれを意識して欲しい」という有難いお言葉。私からも似たような話ですが、セッション開始前に座長さんに挨拶しておいてコメント貰いやすくしとこう/コメント貰ったらセッション終了後にお礼良いに行くとその時に貰えなかった詳細コメント貰えることも/企業さんもあちこちにいるので接点持ってみるのも手/展示ブースとかではあれこれ貰えることも/専門書割引販売してることも良くある、とか。