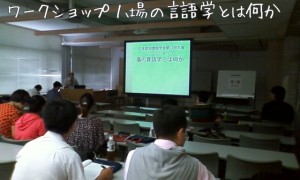日本認知科学会第29回大会 2日目
金曜日, 12月 14th, 2012twilog
認知科学会第29回大会の2日目が終了しました。
文楽人形遣いにおける「言葉や視線を伴わない協調動作」を実現させている「認知」についての話は、操作している「人形」を通してのインタラクションがありそうなんだけど質問する時間がなかったな。
昼ご飯はコンビニパンで済ませて近場散策。公園かと思って歩いてたら仙台城跡付近だったらしい。いや、近くにあるのは地図見て知ってたけどこんなに近い(会場から徒歩数分)とは思ってませんでした。正確には博物館がその距離にあって、博物館を挟んで反対側にあるからすぐにはつかないんですが、それでも近い。ということで一応伊達さんに挨拶してきました。
特別講演は東北大学・邑本俊亮先生の「実践的防災学」。もともとは文章や言語理解における認知心理学が専門だったのが、(3.11前から)いろいろあって災害科学国再研究所として認知科学に求められていることとして基礎研究だけじゃなく応用研究もやることになったとのこと。文章理解と認知についての出発点を探すことが今回の目標の一つだったので、戻ったら関連事例を読み漁ってみよう。
シンポジウムでの「OS型言語」が謎だったんですが、SVOとかのOとSでした。世の中のほとんど(96%強)はSの後にOが出現するけど、そうじゃなくてOが先に出る言語を「OS型言語」と呼ぶらしい。研究的にもSO型言語ばかりが対象になってて、それだと見えて来ない言語認知があるんじゃないかという話。
晩ご飯は炭焼き牛たん おやまにて牛タンシチューとテールスープ。炭焼き意味無いじゃんとか思ったら負けです。牛タンはやっぱりシチューの方が好みかなー。初日に食べた焼かれたやつも美味しいけど、折角だからあれこれ食べてみないとね。
2日目のプログラムは以下の通りです。
口頭セッション3: 芸術
ポスターセッション3
特別講演: 実践的防災学が認知科学に期待するもの
口頭セッション4: 視覚・認知
シンポジウム1: 「主語・目的語語順選好」は普遍的か:主語末尾型言語からの検証
以下、Q&Aを中心にした備忘録です。例によって當間解釈によるメモです。
<目次>
[ 口頭セッション3: 芸術 ]
- O3-1: 文楽人形遣いの阿吽の呼吸, 植田一博(東京大学大学院情報学環/日本科学技術振興機構CREST)ら
- O3-2: 文楽人形遣いにおける演技動作と呼吸の対応関係, 渋谷友紀(東京大学大学院学際情報学府)
- O3-3: 演劇初心者の演技計画における熟達支援の効果, 安藤花恵(九州国際大学法学部)
- O3-4: 音楽の終止構造認識時の脳活動, 星‐柴玲子(東京大学大学院総合文化研究科)ら
[ ポスターセッション3 ]
- P3-2: 他者作品との関わりを通した表現の自覚性獲得過程についての検討, 石黒千晶(東京大学大学院情報学環学際情報学府)ら
- P3-4: 人生を表象する映像作品の修辞と概念再考的認知:ストーリーは邪魔者か?, 小川有希子(法政大学社会学部)ら
- P3-9: 描画コミュニケーション実習に関する予備調査:実験のデザインに向けて, 田中彰吾(東海大学総合教育センター)
- P3-12: 状況とルールのパターンマッチングを学習するシステムの構築と評価森田純哉(北陸先端科学技術大学院大学)ら
- P3-23: アイディア生成プロセスにおけるドローイングの認知作用に関する予備的研究, 江口倫郎(東京大学大学院学際情報学府)ら
- P3-24: 三次元面知覚の定量評価, 松原和也(東北大学電気通信研究所)ら
- P3-25: 日本地図描画課題を用いた不完全な知識に基づく意思決定メカニズムの分析, 山本紘之(北陸先端科学技術大学院大学)
- P3-27: 比喩にかかわる意味特徴が理解容易性、面白み、斬新さに与える影響‐直喩形式と隠喩形式の比較‐, 中本敬子(文教大学)ら
- P3-30: 『いわての民話KOSERUBE』―プロップによるストーリー生成システムをベースに文・音楽・視覚表現の生成を統合したシステム―, 今渕祥平(岩手県立大学大学院 ソフトウェア情報学研究科)ら
- P3-31: 言語隠蔽効果における言語化内容の質について−距離推定課題による検討−, 武長龍樹(東京大学先端科学技術研究センター)
[ 特別講演 ] : L2: 特別講演: 実践的防災学が認知科学に期待するもの, 邑本俊亮(東北大学)
[ 口頭セッション4: 視覚・認知 ]
- O4-1: 潜在的な快感情の喚起による視覚情報処理範囲の拡大, 藤桂(筑波大学人間系)ら
- O4-2: Gaze-contingency パラダイムを用いた乳児における行為の意図性の評価, 宮崎美智子(玉川大学脳科学研究所)ら
- O4-3: 注視から認知過程へ:ベイズ統計による次元選択・潜在集団の推定, 日高昇平(北陸先端科学技術大学院大学)ら
[ シンポジウム1 ] : S1: シンポジウム1: 「主語・目的語語順選好」は普遍的か:主語末尾型言語からの検証
口頭セッション3
O3-1: 文楽人形遣いの阿吽の呼吸, 植田一博(東京大学大学院情報学環/日本科学技術振興機構CREST)ら
文楽人形遣いにおける協調動作はどのように実現しているか? 主遣いは「ず(と呼ばれる命令)」を発していると言われている。 左遣いの視線計測->ほぼ人形動作を見ている 人形動作計測(磁気式モーションキャプチャ) -> 主遣いによる先行->左遣いが合わせる->同期(ウェーブレット変換で位相差解析) 脚本や「床(三味線や義太夫節)」の有無で同期に差があるか 差がないなら「ず」が主要因 ヘッドフォンで主遣いのみに動作を指示した場合でも、 主遣いと右手遣いはほぼ同じ(高い正の相関)。 左手遣いはやや遅れるが、それなりに相関。(遅れても見た目はほぼ再現) 床が無くても動作再現できるが、動作の大きさに違いが生じる naltoma: 人形操作においては視線や発話による合図を行えないとのことだが、 演台や主遣いの直前までの演出からどのような流れが続きそうかを推測することで 協調的動作を実現している?(これが「ず」?) naltoma: 頭巾を被っている方の視線を見ることはできないが、 被っている方からはどの程度の情報を目視できるのか?(ゼロと看做して良い?) naltoma: 入念なリハーサルを行わない即興芸術というのは、 見方によっては「ある一定範囲内に収まっていれば良い」という範囲内に 収める協調動作になっていれば良い? naltoma: 人形操作において、3人の役割として分割されているが、 これはどのぐらい独立しているのか。操作や人形自体を通して 「相手に伝わる/伝えられる」情報は考慮しなくていいのか? Q: 主遣いと左遣いの間について検証されているが、 足遣いは視覚的なアクセスが困難。足遣いについて何か知見があるか? 「ず」に含まれる情報としては、 返しのタイミング、動きの大きさ、スピードぐらいの要素が入っていそう だが、タイミングはズレるが動きの大きさは合っているなど、「人形の 動き」についてある程度型が分かっていれば追従で実現できそう? A: 足遣いについては、基本的に主遣いの腰に手を当てており、 肉体的にダイレクトに伝えられると言われている。今後の課題。 「ず」にどういう情報が含まれるかについては、 今回は同期でのみ分析しているのでタイミングに情報がありそうだという ことぐらいしか言えない。違う動作でも波形としては区別できない。 人形遣いは区別できるので、それを探している最中。 Q: 今回の例では明らかに右手が先に出ているが、そういう動作が多い? 最初から同時動作というような時にはどうなる? A: 型動作については右手先行になるはず。 演目で脚本が分かってる場合には同時もあり得る。 「ず」に見えるけど「ず」として悟らせない所に面白みがありそう。
O3-2: 文楽人形遣いにおける演技動作と呼吸の対応関係, 渋谷友紀(東京大学大学院学際情報学府)
芸の「呼吸」:重要視されるが極めて多義的 狂言・歌舞伎: 熟練するにつれて動作と呼吸相が非同期的になる 文楽人形遣いでは 動作と呼吸の同期性についてどうなる?(関係性検討) 呼吸曲線の周期性は?(呼吸に乱れが無いか、一定になされているか?) 熟練者は、そうでない人より動作と呼吸が互いに独立。 naltoma: 呼吸動作が何かしらの「同期」情報になっている? naltoma: 熟練になると動作と呼吸相が非同期的になるというのは、 呼吸に引きずられること無く動作を行える「一種の達人」みたいなもの? そういう熟練者が主遣いで残りがそうでない場合、 全体として動作が成立しにくいということは起こらない? (非熟練者側が合わそうとするので問題にはならない?) naltoma: 逆説的に、呼吸を安定させるにはどうしたら良いのだろう? Q: 舞台歴と役割が相関していそう。 浄瑠璃が入ってきたときの差についても同じことが考えられないか。 A: 主遣いで比較している。13年の方も主遣いでの比較。 舞台歴と主遣い/左遣いとの差はある。 31年の方は基本的には主遣いをしているが、 より芸歴が長い人の左遣いをやることもある。 Q: 13年の人は呼吸が乱れているのは、外の情報を取り込んでいるようにも思う。 乱れていないのは慣れてしまって外からの情報に気を配っていないという印象を受ける。 呼吸が乱れないながらも外に適用していっている? A: 外の情報を主遣いがどのように取り入れるかということについては、 芸団で言われていることとしては「浄瑠璃の情報をどう受け取るか がとても大切」で、演奏者毎の違いもあり聞きながらやる必要がある。 良く分からないが、浄瑠璃とべったりになってはいけないと言われることもあるらしい。 呼吸の安定は体の方であたふたしないということを表していると思う。 Q: 実際に見て「呼吸が乱れている」というのは見えるのか。 動作に合わせて呼吸しているのは、ある意味迫力にも繋がりそうだが。 A: 役柄やその性質にも関係していると思う。 今回の女形だと「よいしょ」という感じはあまりない。 時代物や、型が連続して行く場面では人形遣い自身の動きが大きくなることもある。 その時はまた異なる呼吸との関係が見れると思っている。
O3-3: 演劇初心者の演技計画における熟達支援の効果, 安藤花恵(九州国際大学法学部)
熟達化研究:ある領域での「初心者」と「熟達者」を比較 明らかになること:差 明らかにならないこと:成長プロセス、その差を埋めるための支援法 -> この差を埋めるための研究 演劇俳優の熟達 初心者は脚本解釈は考えるが、演技計画(どう演技するか)をほぼ立てない 準熟練者(5年〜)は観客視点/共演者/脚本全体を考慮して演技計画を立てる -> 初心者にさまざまな種類の演技計画を立てるよう指示したらどうなる? 観客への見え方を意識して計画立てるよう指示したらどうなる? 実験群 自由に演技計画を立てる 脚本Aについて熟達支援して演技計画を再度立てる 脚本Bについて自由に演技計画を立てる 統制群 熟達支援無し 熟達支援:紙面と口頭 分析方法:発言数をカウント 演技計画/観客への見せ方を意識している発言 文脈や流れを考慮している発言/バリエーションの数 結論 「態度」を身につけることについては、簡単な指示を出すだけで効果がある。 今後の課題 さらに準熟練者(質や量)に近づけるには? より長いスパンでの効果? naltoma: 成長プロセス等の「明らかにならないこと」は、 何を比較するかの違いでは? naltoma: 熟達支援の仕方そのものはどう統一した?->紙面+口頭読み上げ1度 naltoma: 今回の実験設計では近視的に最適化した行動を取っているだけということは? Q: 実験にどれぐらい時間をかけた? 実際に演技ができないので最初に戻るといったことはないか? A: 人によってばらばら。話す時間が長い人も入れば、すぐ終わる人もいて、 だいたい30分〜1時間。 演技時に計画通りにできずにつまづくことや、 計画自体が正しくないこともありうる。 Q: 演出と演技指導、気づきとの違いは? 系統立てられた教育がないとのことだが、海外でやられてるような事例を持ってくることは? A: 名演出家とか演劇学科とかあるが、 話を聞く限りでは日本では「その人それぞれ」でやられているように感じた。 Q: 指導する側の熟達は? それを教育に取り入れることはできないか? A: 恐らくその人それぞれのメソッドを持っている。 そこを取り入れることは考えてなかったので、今後考えていきたい。 Q: 茶道では段階的に指示がある。 気にし過ぎてしまってできなくなることはないか? A: あり得ると思う。今回は演技計画に特化してやってみた。 初心者の人はあれこれ計画があり過ぎて演技できないということはあると思う。
O3-4: 音楽の終止構造認識時の脳活動, 星‐柴玲子(東京大学大学院総合文化研究科)ら
音楽を構造化し認識することで意味や情動を含めた理解のレベルが高まる [Koeisch, 2011] 音の流れを、音楽のまとまり構造として認識し分節化することで、内容識別/特徴抽出している? 音楽の最も大きなまとまり(楽章)でfMRI調査した事例 Tonic tone(主音)呈示による安定感 [Krumhansl, 1990] 調整認識のモデル(空間的相関図) 安定感に階層構造がある 終止構造 ドミナントトニック 実験 終止構造1: 和音、旋律ともに終止 終止構造2: 和音は終止するが、旋律は終止しない naltoma: 音そのものの組み合わせで「情動」などを感じるのか? 文化的な活動が重層的に積み重ねられることで「そう感じる」? naltoma: 実際の音も聞いたけど「終止感」自体が良く分からない。。 Q: 1回目の終止感と2回目の終止感は、物理的に何が違うのか? A: 構造の1と2の違いについて、 構造1は和音も旋律も終止し、構造2は和音のみ終止。 旋律単独の終止感を見ている訳ではなく、 和音により構造を作り上げているのかということで検証中。
ポスターセッション3
P3-2: 他者作品との関わりを通した表現の自覚性獲得過程についての検討, 石黒千晶(東京大学大学院情報学環学際情報学府)ら
創作活動(ここでは写真撮影対象で、初学者レベル)において、 自省だけの人と、意図的に「他者作品の模倣課題」させた人を比べると、 その後の聞き取り調査をする限りでは大きな差が見られたという話。 実際の作品での差を見るのではなく、「何を考えて作成すべきか」といった ことについての意識差を聞き取り調査して比較。 創作活動なだけに「うまく表現できないケース」というのがありそうなんだけど、 そこら辺は現時点では考慮していない。また、逆に「こうしたら」とかいう 指導が邪魔してしまうこともありそうなんですが、今の所は観察できていないっぽい。
P3-4: 人生を表象する映像作品の修辞と概念再考的認知:ストーリーは邪魔者か?, 小川有希子(法政大学社会学部)ら
「ストーリーが邪魔」ってどういうことなのかと思ったら、 映像作品鑑賞時の姿勢が「ストーリー重視かそうでもないのか」というのが問いで、 それを確認するためにこういうタイトルになっているらしい。 ストーリーの功罪と修辞の役割を考察しているようだけど、 何故この二つなのかが良く分からず。
P3-9: 描画コミュニケーション実習に関する予備調査:実験のデザインに向けて, 田中彰吾(東海大学総合教育センター)
一つの絵を二人で描かせるタスクにおいて、言葉を禁止、 身振り手振りだけで合作を作るという過程を観察したらしい。 想像通りの傾向が見れてる気がするのだけど、どこら辺に面白みがあるのだろう。
P3-12: 状況とルールのパターンマッチングを学習するシステムの構築と評価森田純哉(北陸先端科学技術大学院大学)ら
(後で質問しようと思ったけど時間取れなかった) ちら見した印象では、P1-20と同じく、モデルを簡単に記述できるシステムを用意して課題やらせてみるという話っぽいのだけど、Robocodeと比べて何か違う点があるのだろうか。
P3-23: アイディア生成プロセスにおけるドローイングの認知作用に関する予備的研究, 江口倫郎(東京大学大学院学際情報学府)ら
「図」の役割を、文系な学生は「先生が遣うもの」と認識しがちで、 理系な学生は「自分が理解するための道具」と認識する傾向にある というのをあれこれ実際に認知的側面について確認したという話。 そうなの?
P3-24: 三次元面知覚の定量評価, 松原和也(東北大学電気通信研究所)ら
2次元空間に描かれた3D描写の「自然らしさ」みたいなのを数学的に評価しようという話っぽい。
P3-25: 日本地図描画課題を用いた不完全な知識に基づく意思決定メカニズムの分析, 山本紘之(北陸先端科学技術大学院大学)
チラ見ですが、合議みたいな話にも繋がるのかな?
P3-27: 比喩にかかわる意味特徴が理解容易性、面白み、斬新さに与える影響‐直喩形式と隠喩形式の比較‐, 中本敬子(文教大学)ら
直接的な比喩と隠喩における差は、 「目新しさ」については見られない(どちらも正の相関)が、 「斬新さと理解容易性」については隠喩形式でのみ負の相関が見られたらしい。
P3-30: 『いわての民話KOSERUBE』―プロップによるストーリー生成システムをベースに文・音楽・視覚表現の生成を統合したシステム―, 今渕祥平(岩手県立大学大学院 ソフトウェア情報学研究科)ら
初日含めて物語生成してる研究室結構ありますね。 こっちはどちらかというとパラパラ漫画に近い印象ですが、 Proppの「昔話の形態学」で分類されているストーリーグラマー を実装し、実際に昔話風の物語を自動生成してみたという話。 ストーリーグラマー自体を何かしら自動作成するというのとは違うらしい。
P3-31: 言語隠蔽効果における言語化内容の質について−距離推定課題による検討−, 武長龍樹(東京大学先端科学技術研究センター)
チラ見ですが、 言語化することでいくつかの認知課題のパフォーマンスが低下するという 「言語隠蔽効果」なるものがあるらしい。
特別講演
L2: 特別講演: 実践的防災学が認知科学に期待するもの, 邑本俊亮(東北大学)
専攻:言語理解に関する認知心理学的研究 昨年まで:大学院情報科学研究科 1. 東邦大学に研究所ができた 3.11を振り返る 災害研の概要 実践的防災学 一連の災害サイクルとして捉える 事前対策/災害発生/被害波及/緊急対策/復旧復興/将来への備え 全てのサイクルで「どんな実践研究が行えるか」 2. なぜ私が防災研に? メインは言語研究 防災とのかかわり 切っ掛け:2004年演題:認知心理学と防災 防災への取り組み/防災情報の認知/防災教育 災害情報認知研究分野 災害サイクル全般の人間の認知を対象 3. 実践的防災学からの期待 災害認知科学研究の可能性:災害サイクルから見た認知科学研究 事前対策:情報伝達、理解 緊急対策:知覚、判断、意思決定 復旧復興:協調、問題解決 将来への備え:記憶、学習、教育 何が期待されているのか 「では、どうすればいいのですか?」:防災意識を高めるには?迅速に避難させるには?etc… 「あなたの研究でどんな貢献ができるのですか?」(基礎研究だけでは) ->認知過程の解明だけでは終わらない 動き始めたプロジェクト 杉浦「生きる力プロジェクト」:震災時行動の認知科学的分析 細川「震災体験談プロジェクト」: いろんな貢献があっていい e.g., 教育的貢献:日常生活に活かせる学び(後に繋がる) naltoma: 「生きる力プロジェクト」でアンケート調査で知力を洗い出し、 それを測定するための課題設計&脳波測定による突き合わせをするのは良いが、 「テスト(課題)」に落とされた時点で「テストのためのテスト対策」になってしまわないか。 教育としてはどう扱っていくことができるのか。
口頭セッション4
O4-1: 潜在的な快感情の喚起による視覚情報処理範囲の拡大, 藤桂(筑波大学人間系)ら
ポジティブな事項(感情に結びつけられた事象?)が思い出されやすくなる 問題解決、創造的思考の促進 視覚情報処理範囲の拡大 不快感情や中立感情状態よりもより広い範囲に拡大(良いことだけではない) *広い範囲を処理してしまうため局所的な集中で処理できるタスクには遅延が発生 ペンテクニック [Strack et al., 1988] 潜在的水準での快感情誘導でも視覚情報処理範囲拡大が生じるか? ごくわずかな表情筋のみの操作 自覚無く認知処理のあり方が変容している可能性 naltoma: naltoma: naltoma: Q: ペンテクニックで発生しているものが潜在的な快感情だという保証は? A: 加えている状態ではよりポジティブに捉えるという結果が一つ。 デブリーフィングでは快感情については気づいていなかったのと、 くわえているのは辛いという回答。 Q: 似て非なる例だが、潜在的ではなく顕在的にその表情を作る例でも結果は同じではないか。 A: 顕在的な感情でも視野が広がったりという同じ傾向はいろいろ示されている。
O4-2: Gaze-contingency パラダイムを用いた乳児における行為の意図性の評価, 宮崎美智子(玉川大学脳科学研究所)ら
乳児はいつから自分が意図的な存在であることに気づくのか? ブレイクダウン:意図を伴う行為主体感の評価に着目 行為主体感 行為と結果の随伴性の理解 自分の行為がどのように環境の変化を引き起こすのかを予測する 目標に応じた行動調整 目標を叶えるための行為の操作 アイ・トラッカーで視線検出利用:アイ・スクラッチ課題(視線で絵を削りだす) 本当に視線と画面の連動に気づいているか? 視線手掛かりで「行為主体感」を評価 気づいた人と気づいていない人の視線パターンを指針に利用 目標の価値に応じた行動調整(背景の絵の魅力度) -> 動機低減 naltoma: 「削る」前後のアトラクティブを逆転させるとどうなる? 削る前がアトラクティブな写真で、削って行くと白くor黒くなる場合。 単に「より新しい」ところに注目するなら逆でも「連動」に気づけそう。 Q: 成人で気づかなかった人はどのぐらい存在する? A: 自分が見ている点を明示的に表示するとほぼ全員が気づく。 ただ削れるだけで注視点を表示しないと半分ぐらいが気づかない。 乳児では、難しい条件では11人中1人のみ、簡単な条件では12人中8人気づいた。 Q: 大人で「気づいてない」というのが本当に気づいていないのかというと違う可能性。 検出できなかっただけという可能性は? A: 単純なself of agencyだと新生児でも持っている。 今回は視線から確認できるかが主題。
O4-3: 注視から認知過程へ:ベイズ統計による次元選択・潜在集団の推定, 日高昇平(北陸先端科学技術大学院大学)ら
注視もそうだが、複雑なデータをどう分析するか 仮説:特定認知過程の働き 実験:画像等の刺激提示、注視対象・時間計測等 問題点 多数の潜在要因:眼球運動の複雑性(生理的な影響など) 線形 vs 非線形 発達的個人差 vs 多様性 -> 個別ではなく、これら全てを一つのフレームワークで対応したい 注視パラダイムの新たな分析法 ケーススタディ: 視聴覚刺激の連想学習実験 [Wu & Kirkham, 2010] 4つの箱への注視点/時間/割合 箱注視バイアス 手掛かり有無 累積注視時間 視覚刺激の有無 ->等のリッチなデータを組み込んだモデル化し、再分析 over fittingならないように適切な複雑さで適応する仕組みも組み込み済み 多数の潜在要因-> 手掛かりと連想効果を分離 線形 vs 非線形-> 1次 発達的個人差 vs 多様性-> 指定された群ごとの効果に条件間差 Matlabコード公開: Quantitative Linking Hypotheses for Infant Eye Movements naltoma: over fitting対策は具体的にどうやる? naltoma: Q: 次元選択は具体的にどうやる? A: 階層モデルになってて、パラメータに対する事前分布がある。 効果0になるパラメータを除いたりしている。 Q: 顔による刺激は注意を喚起しやすいということはないか? A: そこが本来の目的で、その通りの結果。
シンポジウム1
S1: シンポジウム1: 「主語・目的語語順選好」は普遍的か:主語末尾型言語からの検証
「主語・目的語語順選好」は普遍的か:主語末尾型言語からの検証
企画: 小泉政利(東北大学)
話題提供者: 玉岡賀津雄(名古屋大学),酒井弘(広島大学),杉崎鉱司(三重大学)
指定討論者: 小泉政利(東北大学)
趣旨:小泉政利(東北大学) 例文 常長が 帆船を 建造した。(SOV語順) SO語順選考 96.6% 帆船を 常長が 建造した。(OSV語順) OS語順 3.3% [Dryer 2011] 文理解ではSOVが理解しやすく、産出しやすい。他言語でも多く見られる。 SO語順選考を生み出す要因? 仮説1: 普遍的認知説(人類共通の認知特性?) 仮説2: 個別文法説(処理負荷の問題?) OS型言語の文処理メカニズムに関するプロジェクト 玉岡賀津雄(名古屋大学): 言語理解の観点から VOS言語の一つ: マヤ・カクチケル語 動詞だけに標識付き。目的語も主語も無標。 普遍性とは 単に主語が目的語よりも前に来るだけではなく、 基底に基づいた普遍性 空所補充解析(Gap-filling parsing) を視線検出を利用する課題で間接的に確認 ->カクチケル語の特性 酒井弘(広島大学): 言語産出の観点から 文産出モデル [Ferreia & Sievc, 2007] メッセージの構築 文法役割 語順 -> 漸進的処理+各種アクセス容易性 既存モデルの限界:OS言語ではどういうメカニズムで産出される? 発話とジェスチャー産出には相関が見られない(SO言語と一緒) ジェスチャー産出ではSO言語と同じ傾向 語順だけの相違ではない メッセージの段階で違う考え方をしている訳でもなさそう 文法役割付与の段階で異なる方法を採用している可能性が高そう 効率性の観点からは悪そう(効率性だけでは説明できない) 杉崎鉱司(三重大学): 言語獲得の観点から 幼児を対象とした語順とその制約の獲得(予備的研究) 前提@日本語での事例 基本語順はかなり早い段階から獲得している。 談話上の制約(導入)を守られているとほぼ理解。SOV/OSV 制約(indefinite->definite)を受ける文を対象にVOS VSOで検証 OS型言語の研究(フィールド認知科学)の重要性 カクチケル語の理解:VOS語順が最も処理負荷が低い カクチケル語の産出:SVO語順が最も頻度が高い カクチケル語の理解:3歳児でもVOSが基本語順であることを知っている 理解と産出で選考語順が異なるのは何故か?(他言語では見られない) 語要論的な理由(曖昧性解消)が影響? 人の会話は話題になっているものが先に出やすいことが影響? SO言語に基づいた研究手法自体の妥当性? 被験者のバラツキ? 他OS言語での検証? -> 語順という見方をやめる?(主語の卓立性 [Imamura and Koizumi, 2011]) 違いを問題として捉えるのではなく、 違っているのが正しいものとして説明できないか? 基本語順と再頻出語順が異なるにも関わらず、早い段階から基本語順を獲得できるのは何故? Vを構成する形態素順と後続部との関係性を獲得? mirror principle? 生得的な知識との結びつき? 質疑応答 naltoma: 負荷という観点では、知識を重層的に抽象化して獲得する経験を 通しているうちに、SO語順がアクセスしやすい形で保存されている? naltoma: naltoma: Q: SO語順とOS語順の一般について。 SO語順が圧倒的に高いことを考えると、OS語順を持つ言語には それが許されるルールや手段があるということは考えられないか? 例えば head-marking があることによってOS語順が許されていないか? A: ある手段があってそれが実現されているというのは分かる。 何故特定の言語にしかその手段が出現していないか、という問い。 Q: 2135言語調べたらVOSは40言語、OSVは13語という調査結果が出されていた。 ある地方に偏って出現してたり、文化的な要因は考えられないか。 A: 文化的要因を導入することが可能だとして、どう組み込むかが問題。 可能性はあると思うが、アプローチが思いつかない。 文処理上厳しい(負担が大きい)ということも考えられる。 A: 個数に違いはあるがどちらも2%という割合は同じ。 比較的後になって出現している点と地域性はヒントになりそう。 A: チョムスキーの生成文法も見方(180度回転等)によっては同じ構造に見えなくもない? Q: 言語発生的観点で、例えば命令的(統制的)な発話から始まった? ラテン語はその中間的な位置付け? A: 言語発生的な話は明日ある。 命令的な文という話についてはそういう研究例がある。 命令文が基にあるとしても、それがVが先に来るかどうかは別の議論。 Q: 生成文法的にはどういうことが言えるのか。 VPの中で既に何かが起きているという主張? VSO言語はどういうツリーになっている? A: VSOではSVOからOだけ前に出して動詞をさらに前に出すというような分析が多い。 Q: smallVを先に出してるとかいう話ではないのか? A: conceptualの段階では同じじゃないかという提案。 ラージVの構造では同じであって欲しい。 スモールvの構造で違うので、そこで語順がひっくり返っているということを 考えられると良いが、これから検討。 Q: indefiniteの次にdefiniteという順序は、 新情報の後に旧情報となるが、これはどういうことなのか。 A: 構造的な高さと、それがどういう順番で現れるかには高い相関があると言われている。 SO言語では。構造的な高さの上で高い方が旧情報、低い方が新情報だとすると、 そこから出てくる順番がそう見えてるだけかもしれない。 A: 1文では現れるが、恐らくdiscourseの段階ではそうなっていない。 その方が都合がいい。ただし全てが効率性の点では構築されていない。