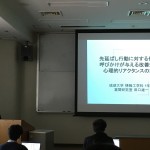なかなか全員が集まらないゼミ
火曜日, 4月 19th, 2016本日のお茶菓子!差し入れ! pic.twitter.com/pZYGR5JHen
— Naruaki TOMA (@naltoma) April 19, 2016
主に就職活動ですが、今の時期はなかなか全員が揃わなくて。個人的には構わないとも思うのですが、その影響で本業であるはずの勉強が疎かになる風潮になり気味なのはややうんざりです。そつなくこなす学生だと割と簡単に終わることも少なくないですが、当然、皆が皆そうだというわけでもなくて。
いろんな考え方があって良いけど、「(考える余地無さ気に)周りに流されるだけで動いてる」というのは「考えてないよな」と見えるだけに、勿体無い時間の過ごし方をしてるなと感じます。
個人的には「考えずに行動するぐらいなら進学してその間に考えたら?」という立場です。個別に顔合わせていうほどでもないですが。自分の道なので自分で考えよう。考え方がわからないならいつでも相談にはのります。